オフィシャルブログOFFICIAL BLOG
オフィシャルブログOFFICIAL BLOG

2014.4.9
こんばんは!
司法書士の立石です。
前回で第10回を迎えた **相続手続きシリーズ**ですが、
今日はお休みをさせていただき、久しぶりに会社の登記について事例をご紹介します。
皆さん、「種類株式」というのはご存知でしょうか?
通常の株式は「普通株式」といって、株式の数に比例した議決権と配当・残余財産の分配を受けられます。
他方、「種類株式」というのは普通株式とはひと味違った株式全般を指します。
たとえば、普通株式よりも多く配当を受けられるとか、
その株式を持っている人がYesと言わない限り議決が通らないとか
どんな内容にするかは会社が株式を発行するときに決めることができます。
実は、この種類株式の内容を発行後に変えるとき、かなり手続きが複雑になるのです。
会社法は「株主の平等」というのを理念の一つに置いています。
これに逆らう手続きに関しては、万全の体制を取るように規定されています。
株式の発行時、株式の内容に納得した上で、そのときの金額に応じて出資していただきました。
なのに、発行したあとでその株式の内容を変えるとなると、
変えた株式の方だけでなくその他の株式との権利関係まで変わってしまい、「株主の平等」に反します。
したがって、種類株式の発行後、その内容を変えるという場合には、株主総会だけでなく各種類の株主総会も必要です。
変更内容によっては株主全員の同意も必要になります。
私が今回担当した案件は、もともと普通株式と優先株式を発行している会社で、
優先株式を廃止し普通株式と同じ内容に変えたいという案件でした。
開いた会議は、株主総会と普通株主総会と優先株主総会の3つ。
それぞれの総会で法定の承認を得て手続を進めていきました。
種類株式を発行される会社も増えてきていますが、変更手続には要注意です☆

司法書士 立石和希子

2014.4.7
おはようございます!月曜から絶好調の司法書士の泉です。
この土日は両日ともジムに行けたので、体の調子がすこぶるいい!!
そうそう!
私、オフタイム始めました!!
オフタイムとは、ケータイの電源をオフにする時間のことです。
特に午前中、起床〜8時までと、20時以降は、可能な限り、ケータイの電源をオフにしようと思っています。
ほんで、集中する!
仕事の時間・読書の時間・勉強の時間・趣味の時間・そしてプライベートな時間、どれもとても大切な時間なので、おもいっきり集中したくて、そのためには、ケータイの電源オフタイムがいいかも!ということで、一度チャレンジしてみます♪
また成果報告しますね♪
さて、いい感じに続いております「**成年後見手続きシリーズ**」ですが、なんと!
本日はその第3弾です!前回は、「任意後見制度の魅力♪」についてお送りいたしました。
任意後見制度の魅力⇒http://www.tenroku-izumi.com/blogs/1073/
本日のテーマは「任意後見制度の注意点!!」です。
今日は『4つ』覚えて帰って下さい☆
注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない。
注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない。
注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い。
注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある。
こんな感じです。もうちょっとだけ細かくお伝えします。
【注意点① 本人の判断能力低下後には利用できない】
「任意後見」はあくまでも、ご本人さんとの「契約」でスタートする制度です。契約である以上は、本人に判断能力が備わっている必要があるので、判断能力低下後においては、任意後見制度を利用することが難しくなります。ただ、認知症の症状が出始めていても、その程度が軽い場合には、任意後見制度のうちの「移行型」あるいは「即効型」を利用することができる場合があります♪
(※「移行型」や「即効型」といった任意後見契約の類型については、次回ご説明いたします♪)
【注意点② 判断能力が低下するまでは開始しない】
任意後見制度においては、本人の判断能力が低下する以前においては、任意後見は開始しないのです!よく考えると、当たり前なんですけどね!だって、任意後見制度は、「将来自分で財産を管理することができなくなったときに財産を管理してくれる後見人を予め選んでおく」という制度ですからね。
では、こういう場合はいかがでしょうか。
「判断能力はしっかりしているが、身体的に日常生活等が難しいから、財産管理等の事務を誰かに頼みたい」
こういうご相談、よくあります。このような場合、任意後見制度はすぐには利用できないので、任意後見契約とは別に、財産管理や身上看護等についての民法上の委任契約を結ぶことになります。
そのため、「任意後見契約」「遺言公正証書」「財産管理契約」「死後事務委任契約」を同時に作ることもあります。これで、将来の財産管理はバッチリです
【注意点③ 「取消権の範囲」が少し狭い】
成年後見シリーズの初回に、「法定後見」と「任意後見」の違いについて、ご説明させていただきましたが、後見人の「取消権」の範囲も少し異なります。
法定後見の場合、本人は民法上の「制限行為能力者」に該当するため、行為能力というのが制限させるため、本人のした重要な法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為など一定の場合を除いて、法定後見人等において取り消すことができます。
これに対し、任意後見制度を利用する場合、本人は、民法上の「制限行為能力者」に該当しないので、本人のした行為は、たとえ本人にとって重要な財産処分行為であったとしても、当然に取り消すことができないです。ただ、詐欺や強迫による取消しや、訪問販売でのクーリングオフなどは、行為能力の有無に関わりなく財産管理事務の一環として行使できる権限なので、任意後見人の代理権目録に記載されている代理権に基づいて行なうことができると解されております。
【注意点④ 信頼できる「任意後見人」を選ぶ必要がある】
これは本当に重要です!任意後見制度を悪用するとんでもない悪者も存在しないわけではないので、ご自身の判断能力が十分備わっているときに、心から信頼できる方に、将来の生活設計ビジョンなどを相談しながら、納得のいく任意後見契約を結んで下さい♪
以上です。
このように任意後見制度には、メリットだけではく、デメリットといいますか注意点もあるので、利用をお考えの際には、ぜひ専門家にご相談下さい♪
次週は、「任意後見契約の類型♪」についてお送りいたします。
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
最後まで読んで下さり、本当にありがとうございます!!
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜から絶好調の司法書士の泉でした♪♪
PS.写真は、近所の桜並木です♪とっても綺麗でした☆


2014.4.4
おはようございます。
最近、パソコンをするときは、PC用メガネを着用しています
司法書士の立石です。
今日の**相続手続きシリーズ**は記念すべき第10弾!
ですので、目が飛び出るようなびっくり相続情報をお届けします。
テーマは・・・『今の法律が適用されない相続!!』
現在もちょうど受任している案件にあるのですが、
相続人を考えるときでも、今の法律が適用されないケースがあります。
法律は時代とともに新しくできたりなくなったり、その内容が変わったりしています。
相続に関する法律についても例外ではなく、時代ごとに大きく変化してきました。
相続人や相続分については、どの時代も「民法」で定められていたのですが、
以下、相続に関する法律の変遷をご紹介します。
1.旧民法の時代
(明治31年7月16日〜昭和22年5月2日まで)
2.日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律の時代
(昭和22年5月3日〜昭和22年12月31日まで)
3.現行民法の時代
(昭和23年1月1日〜現在)※昭和37年と昭和56年に一部改正があります。
それぞれの法律の内容については今日は割愛しますが、
1の旧民法は、現在の民法とはまったく内容が異なっています。
これらの法律は、被相続人がどの時代に亡くなったかで使い分けます。
ずーっと昔に亡くなった人の相続登記を今からしようという場合、
旧民法を適用して相続人を考えていく必要があります。
私が現在担当している案件も、被相続人は昭和19年に亡くなっていたので、
旧民法を適用して相続人を割り出していっています。
このように、ずいぶん昔の相続には、現在の民法が適用されないということがよくあります。
現在の相続人や相続分は知ってるよ、という人も要チェックです!!
司法書士 立石和希子


2014.4.2
こんばんは!
あっという間に3月も終わり、新年度を迎え桜が満開になりましたね。
週末のお花見を楽しみにしております、司法書士の立石です。
先週、相続登記の期限はないというお話をしましたが、
遺産分割をされた方々には、ぜひ知っておいてもらいたい判例をご紹介します。
**相続手続きシリーズ**第9弾の今日は、【遺産分割後、登記しなくても大丈夫?】
「法律」とか「判例」になじみがないとちょっと抵抗のある文章ですが、
『不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、
民法第177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、
その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、
自己の権利の取得を対抗することができない。』
という判例があります。
(※判例の文章は、できる限り「、」でつなげようとしているのでしょうか。常に長文です。)
登記というのは、権利を主張するための制度。
例えばこの土地をもらったという人が2人出てきて争いになった場合、
もらったと主張できるのは先に登記をした方です。
(※主張できなかった人は、もともとの所有者への損害賠償請求等は可能です。)
この判例は、
遺産分割協議を行って、自分がその不動産につき法定相続分より多くの権利を取得したとしても、
その登記をしないと多く取得した分の権利は、他人にきちんと主張できない!
ということなんです。
(※民法で定められている法定相続分については、登記申請していなくてもその権利を主張できます。)
例えば・・・を話すと長くなってしまうので事例は挙げませんが、
遺産分割で取得した権利は、登記をして初めて第三者に主張できるということ
をぜひ覚えておいてくださいませ☆
司法書士 立石和希子
※写真は代表の泉と桜です。in扇町公園

2014.3.31
こんばんは!夜が大の苦手の司法書士の泉です!
私の弱点は「夜」です!「夜」には勝てる気がしません!
さて、先週から始まりました「**成年後見手続きシリーズ**」ですが、なんと!
本日はその第2弾です!
本日のテーマは、「任意後見制度の魅力♪」です。
今日は『3つ』覚えて帰って下さい☆
魅力① 将来の生活スタイルを自分で決めることができる♪
魅力② 代理行為・委任の権限が明確♪
魅力③ チェック体制も充実しているよ♪
どうですか?なかなか魅力的じゃないですか?
もうちょっとだけ細かくお伝えしますね。
【魅力① 将来の生活スタイルを自分で決めることができる♪】
将来、判断能力が低下してしまったとき、今まで築いてきたご自分の財産あるいは先代から引き継いだ大切な資産を、どのように管理してもらいたいか、またそれを誰にお願いしたいのか、といったようなことを、本人が任意後見契約によって『自由』に決めておくことができるのです♪
【魅力② 代理行為・委任の権限が明確♪】
任意後見制度を利用されるときには、任意後見人になってくれる方と契約を締結することになりますが、この契約内容は登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明されます。
また、他の相続人から「お金を勝手に使い込んでいるのではないか?」という疑いをもたれたとしても、「本人から委任を受けていること」「何を委任されているか」について明確にすることができるのです♪
【魅力③ チェック体制も充実しているよ♪】
任意後見は、「任意後見監督人」が家庭裁判所に選任されてから開始します。つまり、「任意後見監督人ないしは家庭裁判所が任意後見人をきちんと監督してくれる」というメリットがあります。ですので、任意後見人が他から疑いをもたれる可能性を低く抑えることができるのです♪
いかがでしょうか?
胸がワクワクしますね!
でも、ご注意下さい!!
任意後見制度は、非常に便利な制度ではありますが、気をつけないといけないこともあるのです!
それは、次週のお楽しみ♪♪
なんだか、とてもシリーズっぽくなってきましたね!
来週も張り切ってお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします♪
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
本日もお読みいただき、本当にありがとうございました!!
夜が大の苦手の司法書士の泉でした♪♪
...
2014.3.28
こんにちは!
すっかり暖かくなり、気候が気持ちいいのでウォーキングにはまっております、
司法書士の立石です。
さて、本日も**相続手続きシリーズ**第8弾です!
『相続の手続きに期限があるのか?』
相続の発生後、すぐにご相談にお越しくださる方がいらっしゃる一方、
長年放っておかれる方も中にはいらっしゃいます。
実は、相続登記申請には期限はありません。
(※相続しないという、『相続放棄』の期限は3ヶ月です!!!)
(※『相続税の申告』の期限は、10ヶ月です!!!)
したがって、何年も前に起こった相続の登記を今からすることもできますし、
逆に、相続が起こったからといって焦って登記する必要もありません。
※長年登記をしていない場合のデメリットはこちら
⇒ http://www.tenroku-izumi.com/blogs/1000/
特段の事情がなければ、相続発生後
少し落ち着いたときに手続関係を一斉に整理していかれるといいと思います。
個人的には、半年〜1年のうちに済まされることをお勧めします。
預貯金や証券の手続は、手紙が届いたり通帳が残っていたりと相続人が気づきやすく、
また金融機関に電話すれば取引情報や手続方法をすぐに教えてくれるので
比較的早い段階で済まされる方が多いですが、
登記に関しては市役所や法務局に行ってでないと調査できなかったり
なんとなく登記手続きとなると腰が重かったりして、後手後手になりがちですね。
不動産に関しての相続手続は、
預貯金や証券の手続をその金融機関に相談するのと同じ感覚で、
司法書士に相談してみてください。
どの司法書士も不動産の登記には詳しいですので、解決に導いてくれるはずです。
もし、知り合いに司法書士がいなくてどうしようと思われている方は、
泉司法書士事務所(06―6147―8639)まで、ご連絡ください。
相談は無料です☆
それでは皆さん、よい週末を(^^)

立石 和希子
※昨日も夕方ちょこっとウォーキング行ってきました♪
...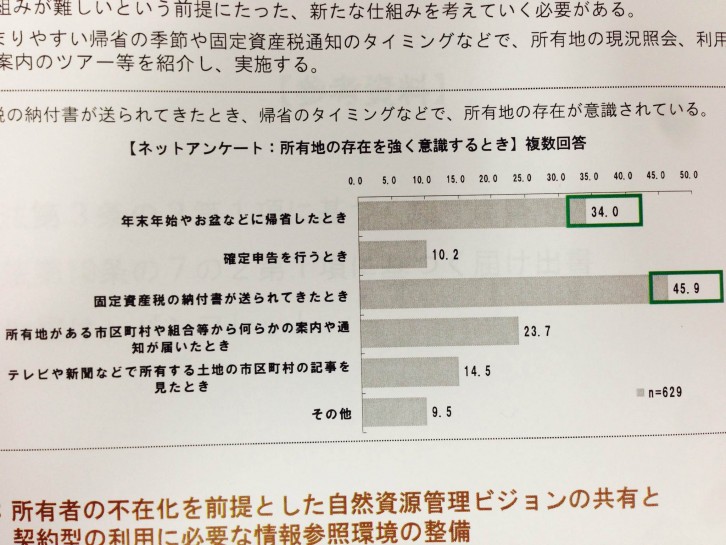
2014.3.26
こんにちは!
司法書士の立石です。
今日の**相続手続きシリーズ**第7弾は、所有不動産の所在・評価額についてです。
皆さん、ご自身がお持ちの不動産について、その所在・評価額等把握されていますでしょうか。普段から気にすることではないので、はっきりとは分からないという方が多いかと思います。
全然チェックしてないという方!
もうすぐチェックできるタイミングがあります。
・・・・市から送られてくる固定資産税納税通知書!!
市区町村によって異なるようですが、
大阪市では4月上旬に固定資産税の納税通知書が送られてきます。
納税通知書には、税額だけでなく固定資産の評価額や物件情報が載っています。
これに記載されている情報は、登記申請の際にも資料として使えたり
確定申告のときにも資料となることがあるようです。
(※非課税の不動産は載らないことがあります。)
皆さん、もうすぐ届きますので大切に保管しておいて下さいね☆
手続きとして今すぐには必要ないという方も多いと思いますが、
自分の財産を把握しておくことは皆さん共通に必要なことですね!
納税通知書、今年は一度じっくり見てみてはいかがでしょうか(^^)
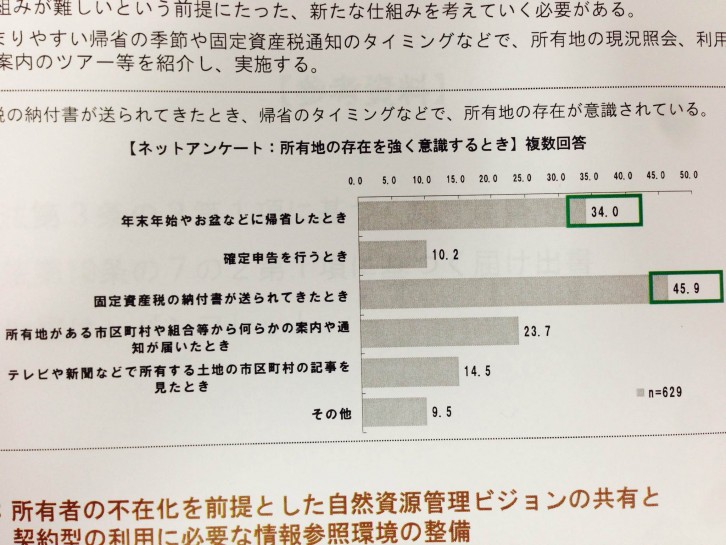
司法書士 立石和希子
2014.3.24
こんばんは!月曜から大奮闘している司法書士の泉です!
前回の「**勝手に相続手続きシリーズ**」の第1弾がとても好調だったので、シリーズ化したいのですが、今日はその想いをグッとこらえて「成年後見制度」のお話をさせていただきます♪
題して,「**成年後見手続きシリーズ**」です!
成年後見制度とは、精神上の障害により判断能力が不十分なため、法律行為における意思決定が困難な成年者を法律面・生活面で支援する制度です。
はい、わかりにくいですね!!
「判断する能力」が低下して、ご自分の財産をきちんと管理できない方のために、きちんと守ってくれる人を選びましょう!
という制度です。
「成年後見」「成年後見」「成年後見」言うてますが、大きく二つに分けることができます。
今日はこの二つだけ覚えて帰って下さい♪
「法定後見制度」と「任意後見制度」です。
法定後見制度というのは、本人の判断能力が不十分になってから、家庭裁判所が支援してくれる人(成年後見人)を選任する制度です。
任意後見制度というのは、まだ、ご本人に判断する能力があるうちに、将来、自分が認知症などで判断する能力で不十分になった際に支援してくれる成年後見人と実際に支援してもらう内容を「予め」決めておきましょう、という制度です。
ズバリ!一言で申しますと、
判断能力がなくなってから「選んでもらう」か、判断能力があるうちに「選んでおく」か。
です。
はい、わかりやすいですね!!
ですので、本日は、ぜひ、この「法定後見制度」と「任意後見制度」の二つの制度の違いをかみ締めながら、美味しいビールを楽しんで下さいな♪
いずみ司法書士事務所は、成年後見制度のご相談をたくさんお聞きします。
「もっと知りたい!」という積極的なそこのアナタ!アナタのことですよ!
いつでもご連絡くださいね♪
本日は、以上となります。
第2弾にご期待下さい☆
「相続」「遺言」「成年後見(財産管理)」「生前贈与」「信託」
私はこの分野のスペシャリストを目指します!!!
というわけで、今週も張り切っていきましょう☆
月曜から大奮闘している司法書士の泉でした♪
...
2014.3.19
こんばんは!
司法書士の立石です。
昨日から胃が痛くて、今日は途中で病院にいきました。
軽い胃腸炎だそうです。
この胃腸炎は厄介で、お腹がすくと胃が急に痛くなります。
胃がグーグーなります。
日ごろブログで、体調には気をつけて下さいと言っている私が
胃が痛くなってしまい、とてもショックです。
皆さん、胃には注意してください!!!
さて、今日も**相続手続きシリーズ**をお送りします。
前々回のブログで、泉が**勝手に相続手続きシリーズ**を書いていましたが、
こちらは元祖の**相続手続きシリーズ**です!
第6弾の今日は、
『相続財産の調べ方』についてです。
相続財産とひとくちに言っても、不動産から動産までさまざまありますね!
まず、皆さんがお調べされるのは『預貯金』ではないでしょうか。
見つかった通帳を記帳してみる。
金融機関に問い合わせてみる。
『株式・証券』についても、各金融機関に問い合わせて調べてもらいます。
『負債』に関しては何も手がかりがないことも多々あるので、
送られてきた請求書・催告書やクレジットカードで調べます。
『不動産』に関しては、納税通知書で大方調べることができます。
ただ、課税されていない不動産(価格の低い不動産や、非課税物件)は納税通知書に記載されていないので、不動産所在地の市役所から名寄帳を取り寄せることで把握できます。この名寄帳を取り寄せてみると、知らない不動産が出てきたり、今ある建物が実はきちんと登記されていないことが分かったりします。
当事務所では、相続財産の調査からお手伝いさせていただきます!!!
特に
○平日は身動きが取れないので、金融機関や市役所に行くこともできない
○長年相続手続きしていなくて、現状がどうなっているか分からない
○自宅以外の不動産がありそうだ
という方は、相続の専門家「司法書士」をご利用されてはいかがでしょうか。

司法書士 立石和希子
※少し遅れてのホワイトデーということで、越さんにプリンをもらいました。
...2014.3.18
おはようございます。泉司法書士事務所の越です。おかげさまで今日もたくさんの申請と完了後の処理があります。(^^)
さて、登記が完了するとその登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において登記識別情報が通知されることになります。
※平成17年以前に登記された方だと登記済証書になります。
(注:登記済証書から登記識別情報への移行時期は、管轄によって異なります。)
登記識別情報とは、登記所が無作為に選んだ「12桁の英数字(AからZまでおよび0から9まで)」です。 現在みなさまがキャッシュカードやクレジットカードで使っている、「暗証番号」と同じように考えていただければ、わかりやすいでしょう。
登記識別情報通知書
平成○年○月○日
○○法務局登記官○ 印
次の登記の登記識別情報について、
下記のとおり通知します。
不動産の表示 ○市○町○番
(家屋番号○)
不動産特定番号 ○○
登記の目的 ○○
受付番号(順位番号)○(○番)
登記名義人の氏名又は名称 ○○
記
登記識別情報
174A23CBAX53
これからは、この番号を「知っていること」が、不動産の権利者としての判断材料のひとつとなります。つまり、不動産を売却したり担保に入れたりする場合には、この『登記識別情報』と呼ばれる「12桁の英数字」を登記所に提示することが必要となるのです
万が一、無くしてしまった場合は?
登記識別情報は,当該不動産に関する所有権の移転の登記などに使用することになりますが,登記識別情報を提供することができない正当な理由があるときは,登記識別情報を提供することなく他の方法により申請ができることとされています。
具体的には,登記識別情報による本人確認に代えて,登記所から登記名義人あてに,「事前通知」(不動産登記法第23条第1項)により本人であることの確認をさせていただきます。
この「事前通知」とは,登記識別情報を提供すべき登記名義人の住所地にあてて,本人限定受取郵便により,登記の申請があった旨,及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知をし,この通知に対して,2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされることをもって,本人からの申請であることを確認するというものです。
また,登記の申請を司法書士等の資格者に委任して行う場合には,「事前通知」の方法によらずに司法書士等の資格者が本人であることを確認した旨の書類(「本人確認情報」)を提供する方法もあります(不動産登記法第23条第4項)
このように無くすと手間がかかる、大変重要な書類ですので大切に保管して下さい。
泉司法書士事務所ではこのような場合でも迅速に対応します。お困りの方はお気軽にご相談下さい。(^^)
...